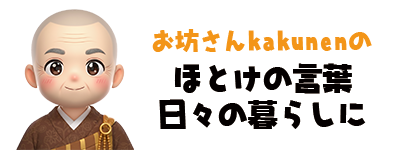「今日も一日、何もできなかった」「また同じ失敗をしてしまった」…。 夜、静かな部屋で一人、スマートフォンの光を浴びながら、そんな風に自分を責めていませんか。
私もかつては自己肯定感というものが非常に低く、他人と自分を比べては落ち込み、自分の至らなさにため息をつく毎日を送っていました。
僧侶という立場でありながら、お恥ずかしい話です。しかし、仏教の教えに日々触れる中で、少しずつ心の重荷を下ろす方法を学んできました。それは、特別な才能や厳しい修行が必要なものではありません。むしろ、今の自分を、そのまま「まあ、いいか」と受け入れるための、ささやかな視点の転換でした。
この記事では、自己肯定感の低さに悩むあなたが、少しでも心を軽くし、自分自身を丸ごと受け入れるための仏教的なアプローチを、私の経験も交えながらお伝えしたいと思います。どうぞ、肩の力を抜いて、お茶でも飲みながらお付き合いください。
なぜ私たちは自分を認められないのか?
そもそも、なぜ私たちはこれほどまでに自分を厳しく裁いてしまうのでしょうか。その大きな原因の一つに、仏教で「執着」と呼ぶ心の働きがあります。
SNS時代の「理想の自分」という呪い
現代は、SNSを開けば、きらびやかな日常や成功体験、完璧に見えるライフスタイルが溢れています。友人や著名人の活躍を目にするたびに、「それに比べて自分は…」と無意識に比較し、落ち込んでしまう。これは、非常に苦しい心の状態です。
私たちは知らず知らずのうちに、「こうあるべきだ」という理想の自分像を作り上げています。仕事ができて、家庭円満で、趣味も充実していて、いつも前向きで…。そんな「完璧な自分」の姿に執着すればするほど、現実の自分とのギャップに苦しむことになるのです。仏教では、この「執着」こそが苦しみの根源であると説きます。
仏教が説く「執着」という心のメカニズム
執着とは、特定の考えや物事、状態に心が強く囚われて、そこから離れられない状態を指します。「理想の自分にならなければ、自分には価値がない」という思い込みも、強力な執着の一つです。
しかし、考えてみてください。その「理想の自分」とは、一体誰が決めたものでしょうか。社会の価値観、親の期待、あるいはSNSで見た誰かの姿かもしれません。それは、本来のあなた自身とは関係のない、外から持ち込まれた「借り物の物差し」なのです。その物差しで自分を測り、足りない部分ばかりを数えていては、心が疲弊するのは当然のことです。
「ありのまま」を受け入れるということ
では、どうすればこの苦しみから解放されるのでしょうか。仏教の答えは、意外なほどシンプルです。「ありのままを受け入れる」ということです。
完璧な人間などいないという真実
お釈迦様は、「諸行無常」という真理を説かれました。これは、すべての物事は常に移り変わり、一定ではない、という意味です。私たちの心や体の状態、能力、そして感情もまた、常に揺れ動き、変化し続けています。
昨日までできていたことが今日はできなかったり、やる気に満ち溢れる日もあれば、布団から出たくない日もある。それが人間という存在の自然な姿です。良い時もあれば、悪い時もある。その両方を含めて「自分」なのです。
「いつも完璧でなければならない」という考えこそが、自然の摂理に反した不自然な状態であり、苦しみを生み出しているのです。
「良い/悪い」のレッテル貼りをやめてみる
私たちは、自分の感情や行動の一つひとつに、「これは良いこと」「これは悪いこと」と無意識にレッテルを貼っています。例えば、「やる気が出ない自分はダメだ」「不安を感じるなんて弱い証拠だ」というように。
しかし、その感情自体に、本来「良い/悪い」の色はありません。やる気が出ないのは、心や体が休息を求めているサインかもしれません。不安を感じるのは、それだけ真剣に物事に向き合っている証拠かもしれません。
ただ「今、自分はそう感じているんだな」と、判断を加えず、事実として観察する。これが「ありのままを受け入れる」ための入り口となります。
心を観察する第一歩:自分の呼吸に意識を向けてみる
「ありのままを受け入れると言われても、具体的にどうすれば…」と思われるかもしれません。そこで、まずお勧めしたいのが、「自分の呼吸に意識を向ける」という、ごく簡単な実践です。これは、仏教的なマインドフルネスの基本となります。
- 椅子に座っても、床にあぐらをかいても構いません。楽な姿勢で背筋を軽く伸ばします。
- 目を閉じるか、半眼にして視線を斜め下に落とします。
- ただ、自分の呼吸に注意を向けます。鼻から息が入り、お腹が膨らみ、そして鼻から息が出ていき、お腹がへこむ。その一連の流れを、ただ感じます。
- 途中で様々な考えが浮かんできます。「晩御飯どうしよう」とか「あの仕事、大丈夫かな」とか。それは自然なことです。考えが浮かんだことに気づいたら、「あ、今、考えていたな」と認め、そっと意識を呼吸に戻します。
これを一日5分でもいいので、続けてみてください。ポイントは、うまくやろうとしないことです。「雑念ばかりで集中できない、自分はダメだ」などと評価しないこと。雑念が浮かぶのは当たり前。それに気づいて、呼吸に戻る。その繰り返し自体が、素晴らしい練習なのです。
この実践は、自分の心を判断せずに「ただ観察する」という、ありのままを受け入れるための基礎体力を養ってくれます。
まとめ
ここまで、自己肯定感の低さの根源にある「執着」という心の働きと、そこから自由になるための「ありのままを受け入れる」という考え方、そしてその第一歩となる呼吸法についてお話ししてきました。
自分を責める癖は、長年の思考習慣です。すぐに変えるのは難しいかもしれません。しかし、焦る必要はありません。大切なのは、自分を慈しむための具体的な方法を知り、少しずつでも実践していくことです。
この先の有料部分では、さらに踏み込んで、自分自身に優しさを向けるための具体的な実践法である「慈悲の瞑想」のやり方や、日常生活の中で自己受容を育むための具体的なワーク、そして他人との比較地獄から抜け出すための仏教的な智慧について、詳しく解説していきます。
この旅を続ければ、あなたの心はきっと、今よりずっと軽やかになっているはずです。