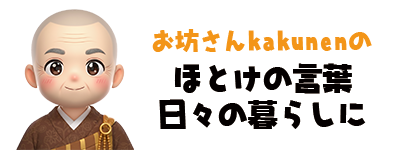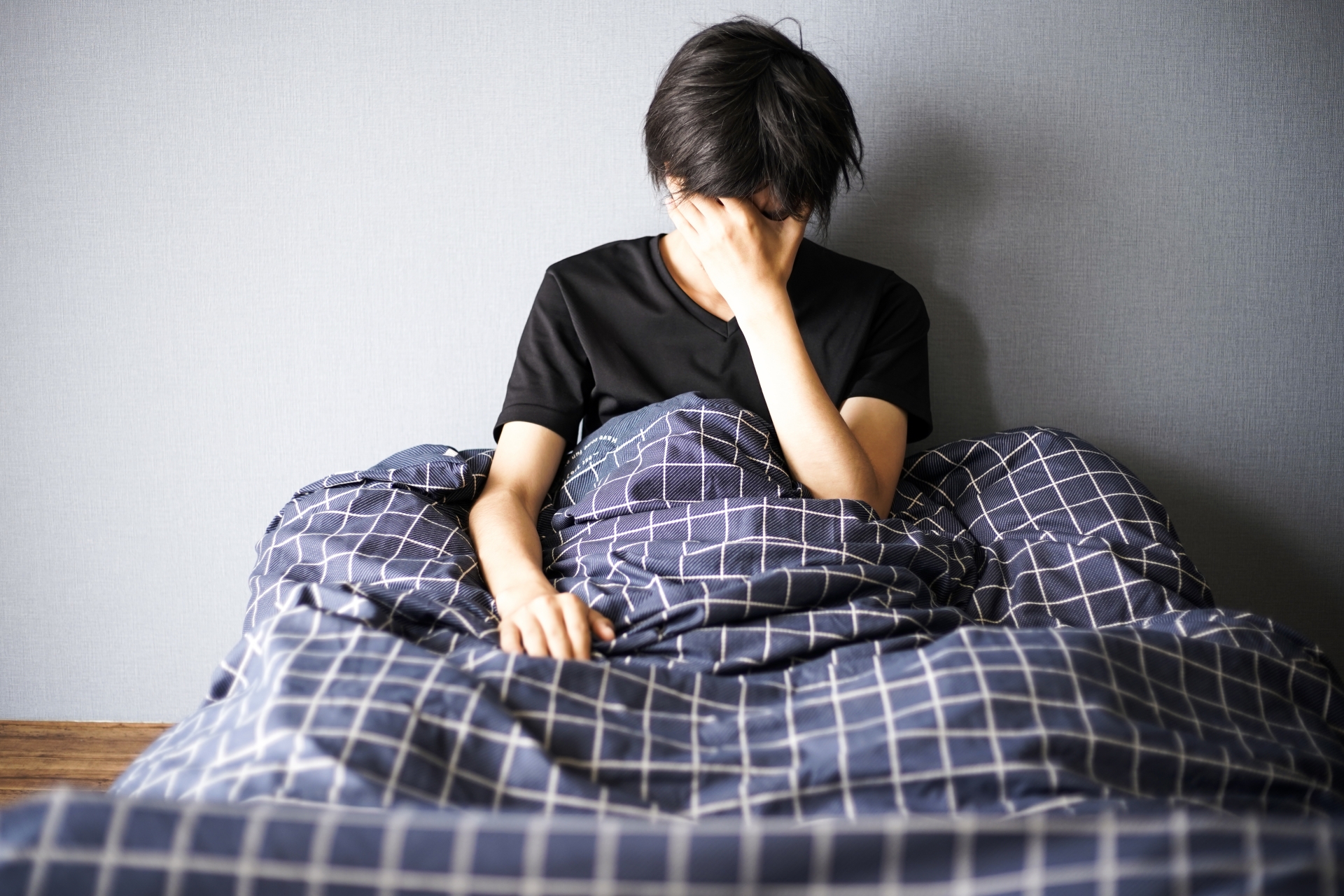はじめに:なぜ、私たちは「あの人」に心をかき乱されるのか
私たちは日々、多くの人との関わりの中で生きています。その中で、どうしても「この人と話していると疲れてしまう」「なんだか棘のある言い方をされるな」と感じてしまう相手、いわゆる「面倒な人」に出会ってしまうことがありますよね。
職場やご近所、親戚付き合いなど、簡単には離れられない関係であれば尚更、その存在がじわじわと私たちの心を蝕んでいく。相手の一言に一日中悶々としたり、顔を合わせるのが億劫になったり。そんな経験は、誰しもあるのではないでしょうか。
しかし、少し立ち止まって考えてみてほしいのです。相手を変えることは、残念ながら至難の業です。ではどうするか。実は、問題の本質は相手にあるのではなく、それを受け止める私たち自身の「心の内」にあるのかもしれません。
今回の記事では、そんな厄介な人間関係を、少しでも軽やかに乗りこなすための「心の護身術」についてお話ししたいと思います。その鍵となるのが、「プライドを捨てたふり」という、一見すると少し消極的に聞こえるかもしれない、しかし非常に賢い処世術なのです。
人付き合いを拗らせる「プライド」という名の鎧
そもそも、なぜ私たちは相手の言動にこれほど心をかき乱されるのでしょうか。その根源には、仏教でいうところの「我」、つまり「自分はこうありたい」「自分は正しいのだから、尊重されるべきだ」という強い思い、いわゆるプライドが存在します。
このプライドは、自分を守るための鎧のように機能することがあります。しかし、時としてその鎧は重く、硬く、私たちの身動きを取れなくさせ、人間関係をギスギスしたものにしてしまうのです。
例えば、誰かに理不尽な批判をされた時。「いや、それは違う」「自分は悪くない」と躍起になって反論した結果、さらに相手を頑なにさせ、泥沼の言い争いに発展してしまった、という経験はありませんか。私も若い頃は、檀家さんとの些細な意見の違いから、つい意地を張ってしまい、後で気まずい思いをしたことが何度もあります。
「自分は正しい」という思いに固執すればするほど、相手の言葉を素直に聞くことができなくなり、小さな火種が大きな争いへと発展してしまう。この重たい鎧を、私たちは無意識のうちに身にまとって、自ら人間関係の難易度を上げてしまっているのかもしれません。
一度、ご自身の日常を振り返ってみてください。どんな時に「カチン」と来ますか? どんな言葉に「見下された」と感じますか? そこに、あなたのプライドが隠されているはずです。
「プライドを捨てる」のではなく「捨てたふり」でいい
「なるほど、プライドが邪魔をしているのは分かった。でも、そう簡単に捨てられるものではない」
ええ、その通りです。プライドや自尊心は、私たちが自分らしく生きていく上で、ある程度は必要なものでもあります。それを完全に捨て去るというのは、聖人でもない限り非常に難しいことですし、その必要もありません。
そこでご提案したいのが、「捨てる」のではなく「捨てたふり」をする、という選択です。
「ふり」と聞くと、なんだか自分を偽っているようで、卑怯なことのように感じるかもしれません。しかし、これは決して自己卑下ではありません。無用な争いを避け、自分の心の平穏を守るための、極めて戦略的で前向きな「心の護身術」なのです。
相手が感情的に何かをぶつけてきた時、こちらも同じ熱量でぶつかっていけば、待っているのは衝突だけです。そこで一枚、相手の熱を吸収する柔らかなクッションを差し込む。それが「プライドを捨てたふり」という技術です。
相手の攻撃をまともに受けず、するりとかわす。これは逃げではありません。自分の心を無傷に保つための、賢い立ち振る舞いなのです。
「プライドを捨てたふり」具体的な3つの振る舞い
では、具体的にどうすれば良いのでしょうか。私が普段から心がけている、誰でもすぐに実践できる3つの振る舞いをご紹介します。
振る舞い1:相手の土俵に上がらない
面倒な相手は、しばしば感情的な言葉でこちらを自分の土俵に引きずり込もうとします。売り言葉に買い言葉で返してしまえば、思うつぼです。大切なのは、相手の土俵には決して上がらない、と心に決めることです。
例えば、相手が強い口調で何かを言ってきたら、一呼吸おいて、「そうなんですね」と静かに相槌を打つ。そして、心の中で「嵐が過ぎ去るのを待とう」と唱えるのです。物理的にその場を「すみません、少し失礼します」と離れるのも有効な手段です。相手と同じ熱量で戦わない。これが鉄則です。
振る舞い2:相手の言葉を「事実」と「感情」に分ける
相手の言葉は、しばしば「事実」と「感情」がごちゃ混ぜになっています。「あなたはいつも仕事が遅い!」という言葉は、一見すると「仕事が遅い」という事実の指摘に見えますが、「いつも」という部分には「私は不満に思っている」という強い感情が込められています。
この言葉をそのまま受け取ると、「いつもじゃない!」と反発したくなりますが、そこをぐっとこらえる。そして頭の中で、「(不満なんだな)…なるほど。それで、具体的にどの件でお困りですか?」と、「事実」の部分だけを拾い上げて問い返すのです。この思考の訓練を繰り返すことで、相手の感情的な部分に振り回されにくくなります。
振る舞い3:「さしすせそ」の肯定クッション
これは、相手の承認欲求を満たし、攻撃の矛先(ほこさき)を鈍らせるための、非常に効果的な相槌の技術です。
- 「さすがですね」
- 「知りませんでした!勉強になります」
- 「すごいですね!」
- 「センスがいいですね」
- 「そうなんですね!」
自慢話や持論を展開してくる相手には、これらの言葉が特効薬になることがあります。心からそう思えなくても構いません。「ふり」でいいのです。相手は自分の話が肯定されたと感じ、満足して攻撃の手を緩めることが多いものです。相手の自尊心を少し満たしてあげることで、結果的に自分の心の平穏が守られる。これも一つの慈悲の形かもしれません。
ここから先は、さらに一歩踏み込んで、こうした「プライドを捨てたふり」をより自然に、そして深く実践するための「心の土台作り」についてお話ししていきます。
小手先のテクニックだけでは、いずれ心が疲弊してしまいます。仏教の智慧を借りながら、そもそもストレスを感じにくい、凪いだ心そのものを育んでいく。そんな、より本質的なアプローチにご興味のある方は、どうぞこの先へお進みください。