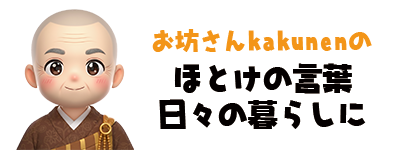私たちの日常に、空気のように溶け込んでいるSNS。遠くの友人との繋がりを保ち、新しい知識や世界との出会いをくれる、大変便利なものです。私も法話の案内や日々の気づきを発信するなど、その恩恵にあずかっております。
しかし、その一方で、ふとした瞬間にスマートフォンを眺めながら、心がざわついたり、見えない疲れを感じたりすることはないでしょうか。仏教の智慧を少しだけヒントにしながら、情報あふれるデジタル時代と穏やかに付き合っていくための、心の持ち方についてお話しさせていただきたく思います。
なぜ、私たちはスマホを手に取ると心がざわつくのか
朝起きてすぐ、あるいは眠りにつく前、無意識にSNSを開いてしまう。そんな習慣をお持ちの方も少なくないでしょう。そこには、友人たちの楽しそうな姿、きらびやかな食事、輝かしい成功体験など、様々な情報が溢れています。
それらを目にすると、私たちは知らず知らずのうちに、自分の日常と比べてしまいます。「それに比べて自分は…」と、落ち込んだり、焦りを感じたり。また、次から次へと流れてくる情報や、絶え間ない通知の着信音は、私たちの心を休ませる暇を与えてくれません。
仏教には「渇愛」という言葉があります。これは、喉が渇いた人が水を求めるように、何かを激しく求め、満たされても決して満足することのない心のはたらきを指します。SNSは、この渇愛を巧みに刺激する仕組みを持っているように感じます。もっと多くの「いいね」が欲しい、もっと新しい情報が知りたい、もっと他人に認められたい。その「もっと、もっと」という尽きない欲望が、私たちの心を疲弊させ、ざわつかせる大きな原因の一つなのではないでしょうか。
心の平穏を取り戻す、住職的SNSとの付き合い方 5つの智慧
では、どうすれば私たちはこの情報の波に飲み込まれず、心の平穏を保つことができるのでしょうか。私が日頃から心がけている、仏教の教えに基づいた5つの付き合い方をご紹介します。
智慧その1:すべてを追わない「諸行無常しょぎょうむじょう」の心
仏教の根本には「諸行無常」という教えがあります。これは、すべての物事は常に移り変わり、決して同じ状態にはとどまらない、という真理です。ネット上のトレンドやニュースもまた然り。今この瞬間に話題になっていることも、次の日には忘れ去られているかもしれません。その全てを追いかけようとすることは、流れ続ける川の水をすべて掬おうとするようなものです。フォローするアカウントや参加するグループを時々見直し、本当に自分にとって大切な縁だけを大切にする。情報の「断捨離」を意識することで、心に大きな余白が生まれます。
智慧その2:デジタルから離れる「静寂」の時間
お寺では、心を落ち着けて自分と向き合う静かな時間が大切にされます。私たちの日常においても、意識的にデジタル機器から離れる「静寂」の時間を持つことが、心の健康につながります。例えば、食事の間はスマートフォンを机の隅に置く。家族と話すときは、相手の目を見て話す。そして、眠る前の1時間は画面を見ずに、静かに本を読んだり、穏やかな音楽を聴いたりする。そうした小さな習慣が、情報によって乱された心の波を、穏やかに鎮めてくれるのです。
智慧その3:比べず、認め合う「縁起えんぎ」の視点
私たちは、SNS上で他人の人生の「ハイライト」ばかりを見てしまいがちです。しかし、仏教では「縁起」という考え方をします。これは、すべての物事は様々な原因や条件が繋がり合って存在している、という視点です。人それぞれ、育ってきた環境も、与えられた役割も、抱えている悩みも全く違います。違う土壌に咲く花を比べて、どちらが優れているかを決めることに意味はありません。他者は他者、我は我。それぞれの場所で、それぞれの花を咲かせている。そう思うだけで、他人への嫉妬や自分への焦りから、少し自由になれるはずです。
智慧その4:内なる豊かさに気づく「足るを知る」の精神
SNSの中の評価や数字に心を奪われていると、私たちは自分の身の回りにある幸せを見過ごしてしまいます。禅の言葉に「吾唯足知(われただたるをしる)」というものがあります。これは、自分にとって本当に必要なものはすでに満たされている、と知ることの大切さを説いています。温かいお茶を一杯いただく美味しさ、窓から差し込む光の美しさ、子どもの寝顔の愛おしさ。そうした、日常に散りばめられた小さな幸せに丁寧に目を向けるとき、私たちはSNSの世界にはない、確かな心の充足感を得ることができるでしょう。
智慧その5:思いやりを届ける「利他りた」の発信
もしご自身が何かを発信する際は、「利他」の心を少しだけ意識してみてはいかがでしょうか。これは、自分の利益のためでなく、他者のためになる行いをしよう、という慈悲の心です。誰かを傷つけたり、見下したりする言葉ではなく、読んだ人の心が少しだけ温かくなるような、あるいは何かのヒントになるような言葉を選ぶ。自分の承認欲求を満たすための発信から、誰かに喜びを分かち合うための発信へ。その意識の転換が、SNSとの健全な距離感を築く上で、大きな助けとなります。
SNSは「諸刃の剣」。振り回されずに使いこなすために
ここまでSNSの心への影響についてお話ししてきましたが、SNSそのものが悪いわけでは決してありません。それは一本の包丁のようなものです。使い方次第で、美味しい料理を作って人を幸せにすることもできれば、誤って人を傷つけてしまうこともある。大切なのは、使う側の私たちの心構えです。
自分が何のためにSNSを使っているのか。時々、その目的を振り返ってみましょう。懐かしい友人との交流のため、自分の学びを深めるため、社会をより良くするための情報を得るため。目的が明確であれば、不必要な情報に振り回される時間も自然と減っていくはずです。自分なりの「SNSとの作法」を持つことが、このデジタル社会を穏やかに生きるための鍵となります。
まとめ
SNSとの距離を整えることは、まるで現代における一つの「修行」のようです。情報の荒波の中で、自分という小舟の舵をしっかりと握り、「今、ここ」という穏やかな港に心を留める。
初めは難しく感じるかもしれませんが、今日お話しした5つの智慧のうち、どれか一つでも構いません。ご自身の生活に取り入れてみてください。きっと、デジタルの喧騒の中にあっても、心の静けさは保つことができるはずです。
この記事が、皆さまの心が少しでも軽くなる一助となれば、幸いです。