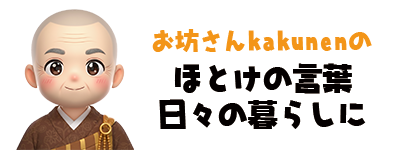日々の暮らしの中で、ふと立ち止まって「ありがとう」と、心からの感謝を感じる瞬間はありますでしょうか。
住職としてお寺におりますと、多くの方が様々な想いを抱えてお参りに来られます。その姿を拝見するたびに、現代社会を生きる皆様が、いかに多くの情報と時間に追われ、心休まる暇もなく過ごされているかを痛感いたします。
私自身が大切にしております教えの一つに、「場に礼すること」がございます。これは、お寺の本堂に入る際に一礼するような、特別な作法だけを指すのではありません。私たちの心を豊かにし、人生をより深く味わうための、古くから伝わる智慧だと感じています。
効率や成果が優先されがちな世の中ですが、だからこそ、私たちが日々身を置く「場」に対し、意識的に感謝や敬意を払うことには、計り知れない価値があるのです。
なぜ「場に礼する」ことが大切なのでしょうか
「場に礼する」と聞くと、少し堅苦しく感じられるかもしれません。しかし、その本質は非常にシンプルで、私たちの心に寄り添うものです。
感謝の心を育む
まず、それは感謝の心を具体的に形にする行為です。私たちが存在するこの空間、そこで暮らしを支える様々な物、そして目には見えないけれど確かにそこにある恩恵に対して、「ありがとう」という気持ちを持つこと。お寺であれば、ご本尊様はもちろん、お堂や境内の木々、ご先祖様が大切にしてきたものすべてが、感謝の対象となります。
敬意の表れ
次に、それは敬意の表れでもあります。その場が持つ歴史や、そこで営みとして紡がれてきた人々の暮らし、そしてその場を大切に守り、育んできた過去の多くの人々への敬意です。それは、過去から現在、そして未来へと続く、大きな時間の流れの中に自分が存在していることを意識することにも繋がります。
心の平安をもたらす
さらに、場に礼することは、心の平安をもたらす効果があります。心を込めて一礼する、その一瞬、私たちは日常の喧騒から離れ、自分自身の内面と向き合うことができます。慌ただしい日々の中で、意識的に立ち止まり、心を静める時間を持つことは、心の安定に不可欠な行いと言えるでしょう。
繋がりを意識する
そして、あらゆるものとの繋がりを意識することにもなります。私たちは決して一人で生きているわけではありません。仏教では「縁起」という考え方を大切にしますが、まさに自分を取り巻く環境、人々、そこに存在するあらゆるものとのご縁によって、今の自分が成り立っています。その繋がりを感じることで、私たちは大きな存在の一部であるという感覚を得られ、孤独感が和らぎ、深い安心感に包まれるのです。
暮らしの中で実践できる「場に礼する」具体的な方法
「場に礼する」ことは、決して特別な場所や状況に限られたことではありません。私たちの身近な日常生活の中に、その実践の機会は溢れています。
自宅にて~一日の始まりと終わりに~
自宅では、まず玄関に一礼することから始めてみてはいかがでしょうか。「いってきます」と「ただいま」の際に、私たちを迎え入れ、送り出してくれる場所への感謝を込める。それは家族の安全を願う祈りにも似た行為です。リビングで家族と過ごす時間、寝室で一日を終える時、それぞれの場所が与えてくれる安らぎに意識を向けてみましょう。朝、起きたら布団を整える、使った場所をきれいにする。そういった小さな所作も、場への感謝の立派な表現です。
職場にて~働く環境への敬意~
職場でも同じことが言えます。毎日使うデスク、意見を交わす会議室、同僚と共有する休憩スペース。そこで仕事ができること、多くの人々と協力し合えることへの敬意を持つこと。一日の業務を終え、退社する際に、自分の机周りを整理整頓し、「今日も一日ありがとうございました」と心の中で呟いてみる。それだけで、明日への活力も湧いてくるものです。
外出先にて~公の場での心構え~
公園で自然の恵みを感じ、お店で心のこもったサービスを受けることに感謝し、公共交通機関で安全に移動できることに心を配る。例えば、電車に乗る前、降りた後に、その車両や運転士の方に感謝の念を抱くことで、日々の移動が単なる時間の経過ではなく、より有意義なものに変わります。
食事の場にて~命をいただくということ~
「いただきます」「ごちそうさま」の言葉に、どれだけの心を込められているでしょうか。目の前にある、動植物の尊い命への感謝。そして、その食事を作ってくれた人、運んでくれた人、食材を育ててくれた人への感謝を忘れないこと。一つ一つの食材が私たちのもとに届くまでの背景に思いを馳せることで、食事が単なる栄養補補給ではなく、多くの命と人の働きに支えられた、尊い営みとして感じられるようになります。
自然の中で~大いなるものへの畏怖と感謝~
私は時折、娘たちと近所の山を散策します。その度に、山、川、海といった大自然の雄大さ、時に畏怖の念さえ抱かせるその力に敬意を払わずにはいられません。私たち人間を生かし、育む母なる大地に、心からの感謝を捧げる。そうした時間を持つことで、自然との一体感をより一層深く感じられるはずです。
「場に礼する」ことから得られる、人生の豊かさとは
日々の生活の中で「場に礼する」ことを意識的に実践していくと、私たちの人生には、目に見えないけれど確かな変化が訪れます。
日常の些細(ささい)な変化に気づけるようになる
これまで当たり前だと思っていたことの中に、感謝すべき多くの事柄が隠されていることに気づけるようになります。雨上がりの虹の美しさ、道端に咲く小さな花の健気さ、家族が淹れてくれた一杯のお茶の温かさ。そうした日常の何気ない風景に感動し、感謝できるようになるのです。
人間関係が円滑になる
場への敬意は、巡り巡って、その場にいる人々への敬意にも通じます。相手への配慮や感謝の気持ちが自然と生まれることで、周囲の人々との間に、より温かく、良好な関係性を築くことができるでしょう。家庭においても、職場においても、円滑な人間関係は、私たちの心の安定と幸福に大きく貢献します。
「生かされている」という感覚と、自己肯定感の高まり
感謝の心で周りを見渡すと、自分がいかに多くのものに支えられ、「生かされている」存在であるかに気づかされます。それは、自分自身が決して無価値な存在ではないという、静かで深い自己肯定感へと繋がっていきます。
「足るを知る」心と、満たされた幸福感
そして何より、「足るを知る」という満たされた心境、すなわち幸福感の増幅へと繋がります。感謝の気持ちは、私たちの心を満たし、日々の幸福度を高めてくれます。そして、その感謝の気持ちは連鎖し、周囲の人々にも良い影響を与え、やがては社会全体を温かいものにしていく力を持っていると、私は信じています。
おわりに:小さな実践が、人生を深く彩る
「場に礼する」ことは、特別な儀式や難しい修行ではありません。それは、私たちが日々の生活の中で、意識を少しだけ自分の内側に向けてみることから始まります。
今、自分を取り巻く「場」に感謝し、敬意を払う。
その小さな実践の積み重ねが、やがては私たちの心を豊かにし、人生をより深く、そして幸福なものへと彩ってくれることでしょう。
この記事が、皆様の日常に少しでも温かい光を灯すきっかけとなれば、幸いです。