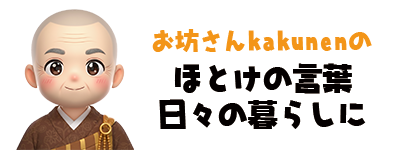はじめに
終活を考え始めたり、日々の暮らしの中で心の拠り所を求めたりするとき、ふと「お寺」とのご縁に思いを馳せることがあるかもしれません。ご先祖様を大切に供養したい、仏様の教えに触れて心穏やかな時間を過ごしたい。その清らかで大切な気持ちは、何にも代えがたいものです。
しかし、その一方で、「お寺ならどこでも安心」と無条件に信じてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と悩みを抱えてしまうケースも少なくありません。特に、永代供養や合同墓などを主軸とした分院や別院が都市部で増えている現代においては、お寺を選ぶための確かな視点を持つことが、未来の安心に繋がります。
お坊さん歴30年以上、住職歴10年以上の私が、素晴らしいお寺様、そして信頼できる住職に出会うために重要なチェックポイントをお伝えします。
幸いなことに、今はインターネットを通じて、お寺の活動の様子や住職の人柄を、ある程度事前に知ることができる時代です。この記事で紹介する4つの視点を持ちながら情報を集め、あなたの心で確かめることで、後悔のないお寺選びに役立ててください。
1、「にぎわい」の奥に、「教え」の心があるか
最近、カフェが併設されたり、マルシェが開かれたりと、誰もが気軽に立ち寄れる、にぎやかで開かれたお寺が増えています。こうした取り組みは、仏様や仏教に触れる素晴らしい「きっかけ」となり得ます。
ただ、ここで一つだけ、心に留めておきたい視点があります。それは、その「にぎわい」が、お寺の本来の目的である「仏教の教えを伝える」という心に、きちんと繋がっているかどうかです。
イベントがお寺という会場を貸しているだけになっていないか。住職の自己満足で終わっていないか。そのイベントは、仏教への「入口」として機能しているでしょうか。楽しさだけで終わらせず、仏教の温かい世界にそっと触れさせてくれるような心配りがあるかどうかは、そのお寺と住職の姿勢を感じる大切なポイントです。
【確認のヒント】
- 「学びの場」は用意されていますか? 「仏教入門講座」や「写経体験会」など、教えに触れる機会を地道に設けようとしているお寺は、教えを伝えたいという誠実な熱意を持っていると言えるでしょう。
- ネットで何を発信していますか? お寺のホームページやブログを見てみましょう。イベントの告知ばかりでなく、法話の要約や、仏教の教えに関するコラムなどが定期的に投稿されているでしょうか。SNSの投稿からも、お寺が何を大切にしているかが見えてきます。
2、その教えは、あなたの心を穏やかにしてくれますか?
お寺選びは、住職という「人」とのご縁を結ぶことでもあります。住職も一人の人間ですから、社会や政治に様々な考えを持つのは当然です。しかし、その個人的な思想が、仏様の教えよりも強く前に出すぎていないかは、冷静に見極めたい点です。
仏教は、私たちの心を穏やかにし、安らぎを与えてくれる教えのはずです。本来、誰の心にも分け隔てなく寄り添うはずの教えが、特定の思想の「道具」となり、自分とは異なる考えの人を遠ざけるような言葉で語られていないか、少しだけ耳を澄ましてみてください。
結局のところ、あなた自身の心が「心地よい」「安らぐ」と感じられるかどうかが、何よりも正直で、大切な判断基準なのです。違和感や居心地の悪さを覚えるなら、そのご縁は慎重に考えた方が良いかもしれません。
【確認のヒント】
- 住職個人の発信をチェックしましょう。 住職個人のブログやSNSでの発信は、その人柄や思想を知る上で、とても参考になります。どのような言葉を使い、どのようなテーマに関心を持っているか。日々の投稿を少し遡って読んでみることで、その方が大切にしていることが見えてくるはずです。
3、「歴史」という時間が教えてくれる、信頼の形
「このお寺は、100年後とは言わないが少なくとも20年くらい後ここにあるだろうか」お墓など、永代にわたるお付き合いを考えるとき、この問いはとても現実的で重要です。そのお寺がこれまで歩んできた「歴史」は、未来への信頼性を測るための一つのバロメーターになります。
何百年もの間、自然災害や時代の変化を乗り越え、地域の人々に支えられてきたという事実は、それだけで大きな信用です。もちろん、歴史が浅いからといって、すべてが信頼できないわけではありません。その場合は、「これから歴史を紡いでいく」という住職の強い覚悟や、明確なビジョンが感じられるかが大切になります。
また、お寺を大切にする「姿勢」は、日々の様子にも表れます。手入れの行き届いた境内、丁寧に修繕された建物。これらは、お寺や、そこに関わる人々を大切にしている誠実な「姿勢」の表れです。
【確認のヒント】
- お寺の沿革を見てみましょう。 公式ホームページに、お寺の歴史が丁寧に紹介されているかを確認します。
- 日々の様子が伝わってきますか? 境内の様子や建物の修繕の記録などを、写真付きでブログやSNSに掲載しているお寺もあります。そうした情報発信から、お寺を大切に守り伝えようとする誠実な姿勢を垣間見ることができます。