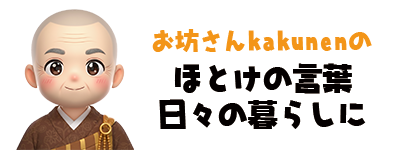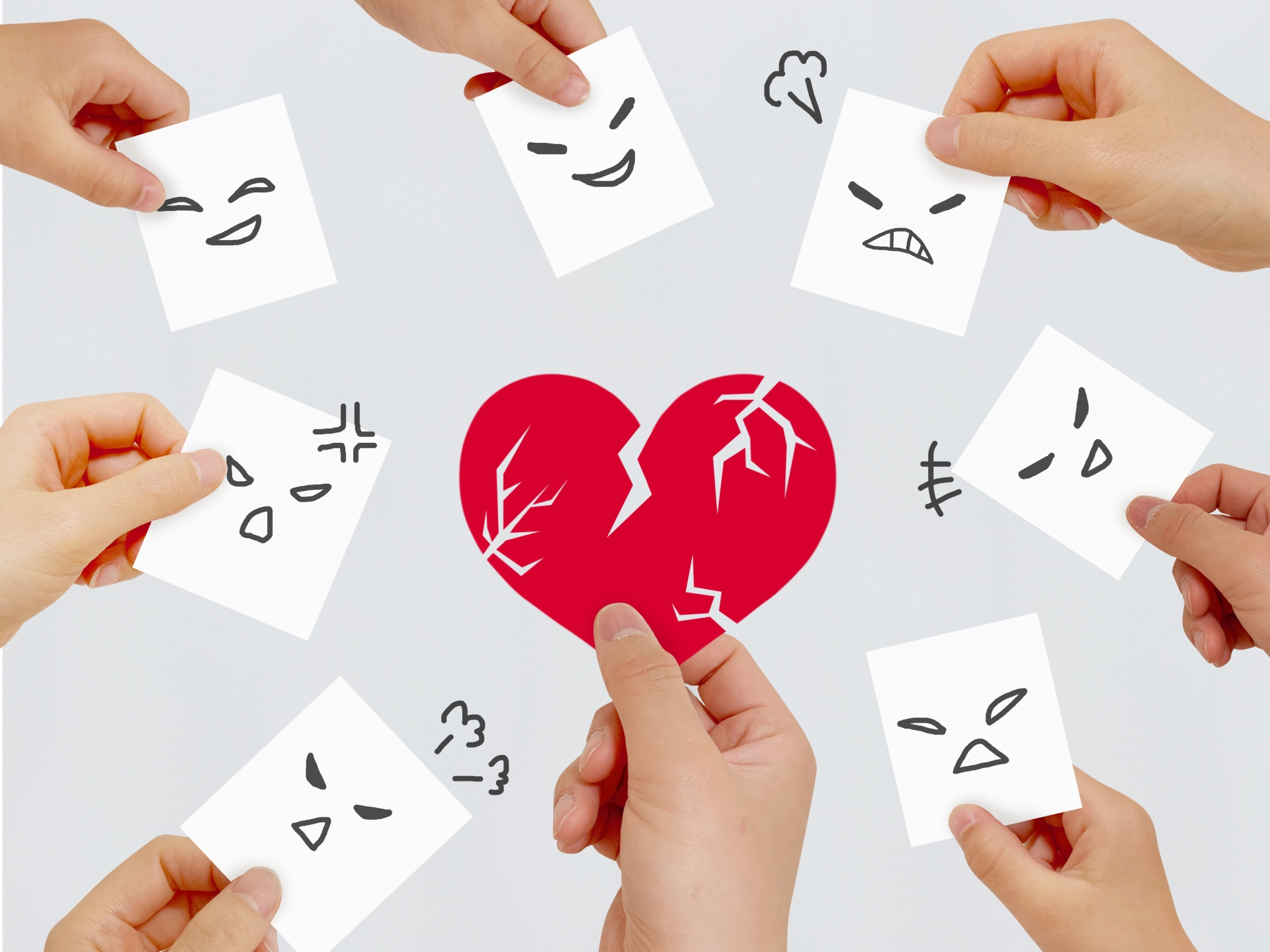お盆は、日本に古くから伝わる祖霊信仰と、仏教の「盂蘭盆会」が融合して成立した行事です。祖先の霊が一時的にあの世からこの世に戻ってくると考えられ、家族がご先祖様をお迎えし、供養する期間とされています。
この「盂蘭盆会」は、お釈迦様の弟子である目連尊者が、餓鬼道で苦しむ母親を救うために、お釈迦様の教えに従って供養を行ったことに由来すると言われています。日本では、飛鳥時代に仏教と共に伝わり、平安時代には貴族社会で、そして江戸時代には広く庶民の間でも行われるようになりました。
地域によるお盆の時期の違い
お盆の時期は、地域によって大きく異なります。
- 新暦7月盆: 東京、横浜、静岡など一部の都市部では、新暦の7月13日から16日を中心にお盆を迎えます。これは明治時代の改暦の際に、新暦に切り替わったためと言われています。
- 新暦8月盆(月遅れの盆): 全国の多くの地域では、旧暦の7月15日に近い新暦の8月13日から16日をお盆としています。農繁期と重なる7月盆を避けて、一ヶ月遅らせたものです。
- 旧暦盆: 沖縄地方など一部では、現在でも旧暦の7月15日を中心に行われます。旧暦は月の満ち欠けによって決まるため、毎年お盆の時期が新暦では変わります。
お盆の過ごし方:ご先祖様をお迎えし、感謝を伝える
お盆の期間は、ご先祖様への感謝の気持ちを伝え、家族の絆を深める大切な機会です。一般的な過ごし方としては、以下のようなものがあります。
盆入りの準備:お墓参りと迎え火
お盆の初日である「盆の入り」(多くは8月13日)には、ご先祖様が迷わず帰ってこられるよう、様々な準備をします。
- お墓の掃除と飾り付け: ご先祖様をお迎えする前に、まずはお墓をきれいに掃除します。そして、お花やお供え物をして、ご先祖様が気持ちよく過ごせるよう整えます。
- 仏壇・精霊棚の準備: 自宅では、仏壇の周りに精霊棚(盆棚)をしつらえ、お供え物を並べます。精霊棚には、位牌を中心に、きゅうりやナスで作った精霊馬・精霊牛(ご先祖様が早く帰ってこられるように、またゆっくり帰れるようにという意味が込められています)、ほおずきなどを飾ります。
- 迎え火: 夕方には、家の門口や庭先で迎え火を焚きます。焙烙におがらを乗せて火を灯し、ご先祖様がこの火を目印に家に戻ってこられるようにという願いが込められています。火を焚くのが難しい場合は、盆提灯の灯りをご先祖様の目印とします。特に、故人が亡くなって四十九日を過ぎてから初めて迎えるお盆を「新盆(初盆)」と呼び、故人の魂が迷わないように白い提灯を飾るのが一般的です。
お盆期間中の過ごし方:供養と家族団らん
お盆の期間中(8月14日・15日)は、ご先祖様と共に過ごす時間と捉え、供養と家族団らんの時間を大切にします。
- お供え物: 仏壇や精霊棚には、毎日新しい水やお茶、食事をお供えします。精進料理が基本ですが、家族が食べるものと同じものを供えることもあります。そうめんや団子、おはぎなどは全国的によく見られるお供え物です。
- 読経: お寺の住職を招いて読経をお願いしたり、家族でお経を唱えたりして、ご先祖様への供養を行います。
- 親族の集まり: 遠方から親族が集まり、故人の思い出話に花を咲かせることも多いでしょう。家族や親族が集まることで、故人を偲び、絆を深める大切な機会となります。私自身も、お盆には遠方の親戚が訪れ、賑やかな時間を過ごします。子どもたちも、普段なかなか会えないいとこたちとの再会を喜び、共に遊びまわる姿を見るのは嬉しいものです。
送り火:ご先祖様を見送る
お盆の最終日である「送り盆」(多くは8月16日)には、ご先祖様をあの世へと見送ります。
- 送り火: 迎え火と同じように、夕方に送り火を焚き、ご先祖様が無事にあの世へ戻れるよう祈ります。京都の五山送り火や長崎の精霊流しなど、地域によっては大規模な送り火の行事が行われることもあります。
- 盆飾りのお片付け: お盆が終わったら、盆飾りや提灯を片付けます。初盆の白い提灯は、お寺に納めたり、送り火で燃やしたりすることが一般的です。
大切なお盆
私にとってお盆は、大切な期間の一つです。お寺では、檀家の方々がご先祖様をお迎えするための準備をお手伝いしたり、法要を執り行ったりと、日々が慌ただしく過ぎていきます。ご先祖様を敬い、感謝する心の尊さを改めて感じる日々です。
お盆休みは、普段なかなかゆっくりと話すことのできない家族と、じっくり向き合える貴重な時間です。子どもたちには、ご先祖様がいて今の自分たちがあること、そしてその命のつながりを大切にすることの意義を伝えて頂きたいと願っています。精霊馬や精霊牛を一緒に作ったり、お墓参りに行ったりする中で、命のリレーを感じて頂ければ嬉しいですね。
また、私自身も、ご先祖様への感謝の気持ちを新たにするとともに、日々の生活の中で見落としがちな家族への感謝の気持ちを再確認する時間でもあります。ご先祖様が繋いでくださった命が、今、私の家族の中で息づいている。このかけがえのないつながりを、これからも大切に守り、次の世代へと受け継いでいくことこそが、私の務めだと感じています。
現代におけるお盆の意義
現代社会において、家族の形やライフスタイルは多様化し、昔ながらのお盆の過ごし方が難しい家庭も増えています。マンション住まいで迎え火・送り火を焚けない、遠方に住む親族と集まるのが難しいなど、様々な事情があるでしょう。
しかし、形式にとらわれすぎることなく、ご先祖様を想い、感謝する気持ちを持つことが何よりも大切だと私は考えます。
- ご先祖様への感謝の気持ちを込めて、仏壇に手を合わせる。
- 遠方の家族や親族と電話やオンラインで交流し、近況を報告し合う。
- 故人の好きだった食べ物を供え、思い出話をする。
どのような形であれ、ご先祖様への感謝と家族の絆を深めることができれば、それこそがお盆の本来の意義と言えるのではないでしょうか。
このお盆の時期が、皆様にとって、ご先祖様への感謝の気持ちを深め、家族の温かさを再確認できる、豊かな時間となることを心より願っております。